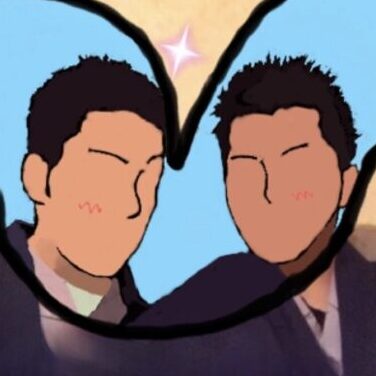皆さんは親子、兄弟、夫婦など家族間でいざという時の財産の相続などの取り決めをしているでしょうか?
よくテレビでも遺産相続問題で、誰が受け取るとか私がいくらとかってトラブルになることが取り上げられています。(お金や資産がからむと豹変して怖い、、)
血縁関係なら自動的に遺産の相続先や配分が優先順位をもとに決まっていきますが、同性パートナーだったらどうでしょう?
養子縁組などで家族関係にあれば別ですが、そうでなければそのままだと後々困ることになるパターンが多いはず。
そこで、僕たちもマイホームという大きな財産を手にしたのをきっかけに何かあっても困らないように相続の際の取り決めをしました。
でもどんな取り決めをするか皆さんは知っていますか??
今回は僕たちがやったことをご紹介します!!
こんな方におすすめ
- いざという時の財産の取り決めを考えている方
- マイホームを持ったのを機に、財産のことも考えている方
- 同性パートナーの財産やいざという時どうするのか気になる方
財産は公正証書で取り決め!パートナーシップでは守られない!
婚姻関係にない同性パートナー。今ではほとんどの都道府県で採用されている「パートナーシップ宣誓制度」。
しかしこれはあくまでパートナー関係ですよと証明されているだけで、お互いに何かあった時に例えば遺産相続だったり意思決定の代理などを保証することはできません。
そこで僕たちが作ったのが「公正証書」
家などの財産に関わることやお互いに何かあって意思決定できないときの代理などを保証し、証明するために3種類作りました。
そもそも公正証書ってなに?
公正証書は公証人に作ってもらうもので、重要な契約や取り決めを簡単には破られないように、しっかり守られるように強い効力を持たせた書類です。
単なる契約書とは違うため、公証人という公務員が依頼人としっかり内容や文章を確認し、さらに証人をたてて作成されます。
公正証書にはいくつか種類がありますが、遺言に関すること、離婚関係、任意後見に関すること、お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)に関することが作られることが多いようです。
そして、これだけ強い効力を持たせて公証人に依頼をして証人までたてて作る書類なのでそこそこの費用はかかるのですが、、(^^;
費用に関しては後ほど、、、!!
ここでは僕たちが実際に作成した3種類についてお話します!
僕たちが作った3種類の公正証書
①遺言公正証書
これはもう遺言書そのものです。
でもこれもちゃんと公正証書にしておけば、いざという時にちゃんと効力を発揮し守られます。
さて、僕たちが家を建てた段階で20代と30代なわけですが若くして遺言公正証書を作りました!
もちろん内容はお互いの財産の相続について。
ざっくりいうと片方が亡くなった時、預貯金や株式等の資産から家まで全てを相手に相続します。という内容にしました。
いつかやろうではきっといつまでもやらないし、今回家を建てたのを機にまとめて作ろうと遺言書も作りました!
ポイント
細かい部分まで決められるので、例えば家は長男に、自分の株式等の有価証券は孫に、預貯金はパートナーになどなど
事前に話し合ってしっかり決めるといいと思います。
もちろん、遺言が無ければ法律にのっとった法定相続順位によって振り分けられてしまいます!
②任意後見契約公正証書
任意後見契約、皆さん知っているでしょうか?
任意後見契約は夫婦やパートナーのどちらかが認知症や病気などで意思表示ができなくなった時、代わりに判断したりできるようにする制度です。
もちろん夫婦やパートナーだけではなく、高齢になった親が認知症になって様々な判断ができなくなった時に代わりに家族が判断したりできるようにする方もいます。
僕たちの場合はお互いに何かがあって判断能力がなくなった時にもう片方ができるように結びました。
パートナーのよーさんが将来認知症になって判断能力が低下した時に、
例えば財産に係る事や保険に係る判断が必要になったとき、本人に代わって僕が判断できるようになるよというものです!
③病院での入院手続きなど家族の代わりにできるようにする公正証書
僕たちのような婚姻関係でも身内でもないパートナー関係では、病院での手続きを代わりにするのが難しいことがあったりします。
例えば、入院の手続きや救急搬送時の対応など。
今では病院によってはパートナーと伝えれば通るところもあるようですが、やはり夫婦や親子、親戚といったちゃんとした身内じゃないとと言われる病院もあるのが現実。
この内容は公証人にはなくても大丈夫じゃないか?とアドバイスをされましたが、僕はいざ何かあった時に病院から断られて対応できないとなってからでは遅いと思い、作成しました。
あれ、任意後見契約でお互いのどちらかに何かあった時に対応できるようにしたのでは?と思いませんか?
僕も最初、思いました。笑
よく説明を聞くと、
任意後見契約は認知症や精神障害などでひとりで決められない、不安があるとした場合に家庭裁判所に申し立て、選ばれた任意後見監督人のもとで始めて代わりに決めたりできるというもの。
あくまで認知症や精神障害などでという場合のみ。例えば元気な若いうちに事故や怪我で入院したから代わりにという場合には適用されません。
若くても何が起こるかわからないので、緊急の時そばにいる自分がすぐに対応できるように、また病院にも証明出来るように作成しました。
3つめはあくまでも一応トラブルにならないようにと作成したものです。
公正証書、作るのにそこそこお金がかかる!
こうして心配性な僕のもとに作られた3つの公正証書。
もちろん作るのにもお金がかかります。それもそこそこ費用がかかるのです、、。
ざっくり僕たちの公正証書の費用は、同じ内容をそれぞれ1部ずつ作成して、15万円ほどでした!
この金額は、遺言公正証書の財産の金額によって大きく変わるみたいですが、遺言に関することが一番費用がかかるみたいです。
実は公正証書、弁護士や司法書士に作成を依頼することも可能。
ただこの場合は弁護士や司法書士が内容を作成、公証役場に行き、手続きをします。
あくまでも本人の代わりをするだけで、最終的に契約して仕上げるのは公証人。
そして、相場にもよりますが弁護士に依頼すると40万〜60万ほどはかかるとか。
4分の1程度の金額で済むのであれば、自分たちで行った方が断然お得です!
僕たちも最初弁護士に依頼しようと見積もってもらいましたが、50万かかると提示され、自分たちで公証役場にいきました笑
弁護士に依頼すると高額だけど、プロならではの経験から文言を入れたり、内容を盛り込んでくれたりもあるかもしれません!
公証役場に自分で行った時の流れ
金額にそんなに差があるなら、自分で行こう!って思ったけど、行ったことないし、そもそも何を用意したらいいかわからないから不安かも、、、
ここまで読んでそう思った方もきっといるはず。 いや、いると信じたい!(笑)
ということで実際に行って作った僕たちの流れをざっくりとご紹介!
まずは事前に公証役場に連絡&予約
僕たちも何もかもわからなかったので、まずは調べて近くにある公証役場へ電話!
大体こういう内容のものを作りたいんです!なんて伝えたら、会う日の予約をして必要なものを確認しました。
ちなみに僕たちが必要だったものは、
・登記書
・パートナーシップ宣誓書
・身分証明書
・住民票の写し
・実印
・現金でしか払えない分の費用
でした。(ちょっと記憶が定かじゃない部分もあるかも)
公証役場を訪問し、書類作成内容を話し合い
予約した訪問日当日、担当の公証人と依頼人とで公正証書の内容を確認しながら話し合っていきます。
僕たちの場合は事前に電話で伝えてあったため、訪問日までに原案として作成してくれていました!
ここでは内容だけでなく、言葉や表現、固有名詞の漢字に誤りがないか、誤字脱字など細かく確認していきます。
将来に関わる重要な取り決めなので、内容に不備や曖昧な部分がないようにしっかり確認していきます。
証人を立てて読み合わせし、全員で確認して署名
内容が確定し、金額を支払ったあと証人をたてるため呼ばれます。
え、どこの誰が証人か? 疑問に思いますよね笑
僕たちの行ったところでは公証人が事前に手配していた法律事務所の事務職員の方2名でした。
調べてみると自分で知人に依頼するのでも可能なようですが、なれる人には条件があるみたいなので要注意。
そこで、依頼人、証人2名、公証人と揃い、全員で一字一句間違いがないか読み合わせて確認、問題がなければ全員が署名して完了となります。
ちなみに証人の方々には証人の報酬として、わずかばかりのお金を包んでいるようです。 あ、これは公証役場からでしたよ笑
まとめ
いかがでしょうか? 公正証書を作成するのにこれだけの費用や人が動いて作成されます。
所要時間はざっと3時間くらいだったと思います!
それだけ財産をいざという時に単なる口約束ではなく、法律の観点からも守り保証してくれる重要なものです。
決して安いものではありませんが、早いうちに財産を守る、遺産に関わるトラブルを避けるためにもぜひ作ってみませんか??
ちなみに公正証書は1度作成したら2度と変更や破棄できないことはなく、作成者のどちらかだけでも身分が証明されれば変更・破棄の手続きができるとのこと。
マイホームを手にした時、結婚した時、終活を始めた時、様々なきっかけやタイミングがあります。
思い立ったその時が良いタイミングかもしれませんよ(^^)
大切な自分たちの財産、トラブルになる前にしっかり取り決めて守っておきましょ!