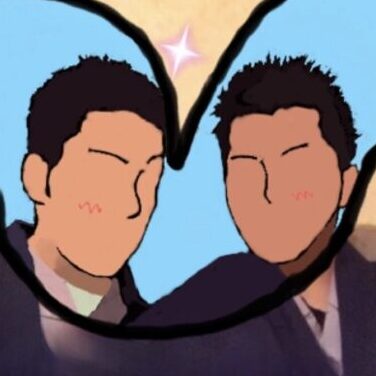環境問題が深刻化し、省エネやSDGsなどと言った言葉や取り組みが当たり前になっているこの頃。
実は最近の住宅も環境に優しい省エネ設計が取り入れられているのは知っていますか?
今回建てた我が家も省エネ設計の家。
省エネ住宅にも色々基準や種類があるのですが、我が家は「ZEH住宅」と言われる種類です。
・・・ZEH。
聞いたことあるけどよくわからない、そもそもなんて読むの?
そんな方もきっと多いはず。
そこで今回は我が家も建てた「ZEH」とは何かをお話していきます!
ZEHってなんて読んでどういう意味?
ズバリ、「ZEH」は「ゼッチ」と呼びます。
近年では省エネ住宅が主流になりつつあるのでテレビなどで聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?
読み方はわかったけど、ZEHってどういう意味なのか。
そもそもZEHは英語の頭文字をとって略した言葉です。
正式には、
net Zero Energy House
(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
と言います。これは、
「エネルギー収支をゼロ以下にする」という意味があります。
これだけだと、ん?どういうこと?ってなりますよね泣
ざっくりいうと、
消費エネルギー(冷暖房など)を創るエネルギー(太陽光発電など)や省エネ対策で0かそれ以下にしようというもの。
つまり、
普段使う消費エネルギーを省エネ対策やエネルギーを作り出してなるべく少なくしよう
ということです。
厳密には細かい決まりや定義があるみたいですが、ここでは単純でわかりやすい捉え方で書いています。
要するに消費エネルギーをなるべく減らそう!ということです!
ZEHには重要な3大要素がある
消費エネルギーを少なくしようという仕組みのZEH。
じゃあ減らすにはどうするかということになるのですが、それにはカギとなる3つの要素があります。
それらが、
「断熱」「省エネ」「創エネ」
そしてこれはZEH認定を受けるのにとても必要な項目となります。
要素①:「断熱」
ZEH住宅は省エネ住宅で、冷暖房や電気の使用量を減らす仕組みが取り入れなければいけません。
夏は冷房、冬は暖房を使う家庭が多いですが、冷暖房を無駄なく効率よく使うには断熱対策が必要になります。
昔の基準で建てられた家でももちろん断熱材等で断熱対策はされています。
しかし今は新たな基準が設けられ、外壁や窓、ドアや家の作り自体も断熱効果がより高まるようなものが開発されているのです。
例えば窓ガラス。
今ではよく見かけるようになりましたが、断熱効果が高まるよう、ガラスが2枚重ねのペアガラス、3枚重ねのトリプルガラスといったものが使われています。
ちなみに我が家の窓は全てトリプルガラスを使用しています!
要素②:「省エネ」
省エネは省エネルギーというだけあって、出来るだけ少ないエネルギーでまかなう冷暖房機器や給湯器、照明などを取り入れる必要があります。
例えば照明だとLED照明、省エネ対応の給湯システムのエコジョーズやエコキュート、エコフィールなどがあります。
もちろん日常での冷暖房や電気の使い方にもよりますが、機器自体を省エネルギーで環境に配慮したものにすることで省エネ効果がかなり期待できます。
LED照明はもはや当たり前になっているくらいの省エネ製品の代表みたいなものですね!
要素③:「創エネ」
創エネはあまり聞きなれない言葉かと思います、僕もあまり聞いたことはありません。
創エネは「エネルギーを創る」という意味で、主に太陽光発電で再生可能エネルギーを創りだして備えておくということがZEHでは必要になってきます。
日中は太陽光発電で電気を創り出し、溜めておいてうまく発電した電気を利用することで消費電力を抑える=光熱費を抑えることを目的としています。
また、発電・蓄電した電気は電力会社に売る事もできるのでちょっとした収益になったりも。
自宅の光熱費を抑えられ、それがエコに繋がるのはとてもいいことですよね!
ちなみに我が家は太陽光発電はなく、創エネの部分がありません。
ZEHには3要素が必要なのに、2つしかない我が家。でもなぜZEH認定されているのでしょうか?
ZEHにも実は種類がある!
実は「ZEH」といっても様々な環境や条件に合わせて種類が分かれています。
戸建て住宅だけではなく、マンションといった集合住宅に適用のものまで!
ここでは戸建て住宅適用のものを中心に見ていきますが、通常の「ZEH」を基準に、
・ZEH
・Nearly ZEH
・Nearly ZEH+
・ZEH Oriented
と分かれています。
各種類の詳しい説明はこちらの記事を参考してみてください。
ちなみに我が家は「ZEH Oriented」が認定されています。
ZEH Orientedとは
簡単に言うと、太陽光発電といったエネルギーを創り出す「創エネ」がいらない認定の種類です。
これは都市部などで土地が狭い、冬に雪が積もることで太陽光が十分に得られないといった理由で太陽光発電などで創エネが十分にできない地域が対象のもの。
ZEH認定条件から創エネの条件のみを差し引いた基準をクリアすれば認められる、「ZEH指向」の種類となっています。
我が家は積雪のある地域の北海道で、冬場の太陽光発電は見込まれないだろうということからZEH Orientedが認定されています。
どうしても冬は雪が積もってしまうと太陽光発電が難しくなってしまう、、
実際にZEH住宅に住んだ感じは?
そんなZEH Oriented の我が家に住んで約半年ちょっと。省エネ住宅に住んだ感じは実際どうなの? と気になる方も多いはず。
そこで住んで感じた事を個人的な感想ですが、まとめてみました!
やっぱり断熱性能は高い
ずばり、断熱性は高いです。そりゃ高断熱の素材や構造なので当たり前なのですが笑
特に感じたのは夏の窓際。
我が家の窓はトリプルサッシの反射ガラスを採用しており、日中、直射日光が当たり続けている南側の窓を触っても熱くなっていません。
また、その周辺の空間の温度も極端には上がっていないのです。
もちろん全く熱を感じないわけではないですが、ずっと太陽光が当たっている割には熱くないです。
また、エアコンもリビングはもちろん玄関や寝室まで家中を1台でまかなっています。
間取り上、全部屋を均等に涼しくすることは難しいですが、それでも断熱性が高いからこそ冷気が逃げて熱がこもって温度が上がることがなく快適に過ごせます。
ただ、どうしても24時間換気システムの都合上、空気を取り込む吸気口からは外の暑い空気が入るのでエアコンをうまく使う必要があります。
それでも高断熱のおかげでガンガンに冷房をフル稼働させなくても効率よく使えば、1台で済ませられたり電気代も安く抑えられるということです。
エアコンの冷気が届きにくい部屋にはサーキュレータを使って風を送っています!!
工務店や設計士によってはもっと綿密に考えられた家づくりをしているところもあり、例えば冬場は日中入る太陽光で室内を温めるおかげで暖房をあまり使わなくて済むような設計だったり、軒を出すことで夏場の直射日光を防いで室内の温度の上昇を抑えるといったアイデアもあります。
(残念ながら、我が家はそのような素晴らしい設計ではないですが、、泣)
高断熱の設計と組み合わせたら、素晴らしい省エネ住宅が出来上がりそうですね!
夏場の電気代は少し安いかも、、?
あくまでも賃貸時代との比較になってしまいますが、体感賃貸の時とあまり変わらないか少し安いかなというくらいです。
新居は賃貸時代よりも広くなったので、基本的な光熱費が高くなるのは仕方ないところ。
住む前は家も大きいし部屋も広いからエアコンも電気代高くなるんだろうなぁと身構えていましたが、思ったよりも高くなかったことに驚き!
これも省エネ住宅の恩恵なのかなと勝手に思っています笑
ただ冬場はパネルヒーターを24時間つけっぱなしなこともあり、エアコンは使っていませんが電気代はそこまで変わらず、むしろ灯油代が結構かかります。
これは寒い冬、家を暖かく保つためには仕方ないのかもと思っていますが、それにしてもこんなにするのかというくらい高く感じました。
ZEHのデメリット
ここまでZEHの特徴といい部分を中心にお話してきましたが、当然デメリットだってあるんじゃないの?と思った方。
もちろん、あります。何でもメリットがあればデメリットもあります!!
ではZEHのデメリットはどんなことでしょうか?
①建築費用がちょっと割高になりやすい
通所の住宅よりも高断熱の素材を使用したり、省エネ設計の設備、太陽光パネルを設置するなど特別なもの使ったりすることもあり費用がやや高くなりがち。
でも長い目を見れば、最初の費用は高いけど省エネで長持ちする家にするのか、最初安く抑えて、省エネではないがために光熱費がかかったり長持ちしない家にするのか、どちらがいいかということ。
最初、多少費用がかかっても長持ちする家に出来るのであればそっちの方がいいかもしれませんね。
②間取りや設計に制限がかかることがある
断熱性能や省エネ性能の基準を満たすためには省エネ、創エネに必要な設備を設置しなければならず、物によっては間取りなどに制限がかかります。
特に太陽光パネルの設置は屋根が重くなるので、十分な耐震設計が必要になります。
せっかく省エネ住宅で太陽光パネルをつけたのに、重くて家がつぶれてしまっては困りますよね(´;ω;`)
そこで部屋の一部、例えば広々したリビングのどこかに柱や壁を余分に増やすなどで補強しなければいけない事があります。
せっかくの大空間のリビングなのに真ん中に柱が、、なんてこともあり得るのですが構造上仕方ないこと。
もちろん、ハウスメーカーや設計士の腕次第ではそうならないような工夫をしてくれることもあるので、相談してみるといいでしょう。
③設備のメンテナンス費用がかかる
これはZEHじゃなくても冷蔵庫や洗濯機などの家電も壊れたら直したり、壊れないよう点検したりなどメンテナンスが必要ですよね。
それと同じく省エネ設備もメンテナンスが必要。
例えば、24時間換気システムのフィルター掃除や耐用年数を迎えたら壊れる前に交換とか我が家のようなパネルヒーターは定期的に中の液を交換しなければならなかったりと省エネ住宅にはない設備のメンテナンスが必要になってきます。
これらも家を長持ちさせて長く暮らすには必要な費用となります。
これからの時代、ZEHが義務化される
ここまで僕が実際にZEHの家に住んだ体験を交えて、特徴やメリット・デメリットをお話してきました。
いいことがたくさんある反面、費用がやや高くなりがちなんてところもあるZEH。
ここでは紹介していませんが、ZEHよりも高い基準の「長期優良住宅」などさらに省エネで家が長持ちするような設計基準があったりします。
そして、地球温暖化が進み省エネに力を入れている近年ですが、2025年4月以降からはこれから新たに建てる新築住宅には省エネ基準をクリアする事が必要となってきます。
また、この記事を書いている段階では、2030年までにはZEH義務化が進み、全ての新築住宅にZEH基準が求められるようなるなんて話もあります。
それだけ家に対してもエネルギー効率が良く、環境にも優しいものが求められる時代になってきているということですね。
環境だけでなく家計にも優しく、長持ちする家は資産価値も高くなるのでいい事ばかり!
また、建築費用が高くなりがちとお話しましたが、その分認定されれば国の補助金もちゃんとあります!
今後はその補助金も幅を広げていくという話もあるようです。
補助金が出るのであれば、安心して長持ちするエコな家を作ることが出来そうです。
どうせZEHが義務化されるなら、今から家づくりをする方はZEHの家を作ってしまう方がお得かもしれませんね!